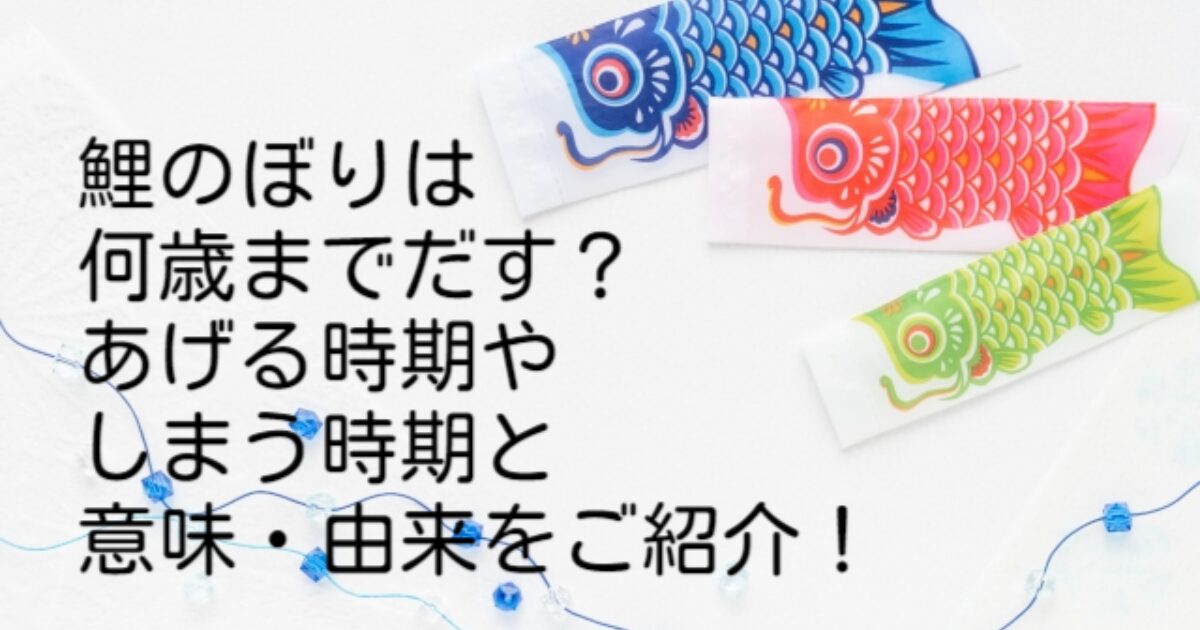毎年あげるのが楽しみな反面、ちょっと大変な鯉のぼり。
縁起物なのでぜひ出してあげたいけど、何歳まで出せばいいのでしょう。
男の子が家にいる限り?
生まれてから数年でいい?
考えることは様々ですが、鯉のぼりを何歳まで出すのかという疑問には、実はちゃんとした答えがあったのです。
今回は、そんな疑問にお答えします!
鯉のぼりって何歳まで出すもの?本来の説とみんなの声を紹介
鯉のぼりを何歳まで出すかについては、いくつか候補を挙げて解説することができます。
- 子供が7歳になるまで
- 子供が小学生になるまで
- 子供の気の済むまで
- 親の気の済むまで

これらの説について、次に詳しく見ていきましょう。
子供が7歳になるまで
これは、古くから伝わる一般的な説です。
鯉のぼりを何歳まで出すのかについての、本来の説とも言うことができますね。
昔は子供の成長率が悪く、7歳を迎えられない子もたくさんいたと言われています。
「七つまでは神のうち」という言葉も伝わっており、これは、「子供は七歳までは神様のもの」という意味です。
つまりは、子供が7歳くらいになるまでは、生きるも死ぬも神様のご意思次第というような意味でしょう。
その年齢まで無事に育ったことを神様に感謝する意味もあり、7歳まで出すのがいいとされているのです。
子供が小学生になるまで
こちらは現代的な考え方です。
鯉のぼりを喜ぶのはせいぜい小学生くらいだろうと考える親は多く、それが鯉のぼりを飾る一つの期限となっているようです。
これは本来の説に重なる部分もありますので、子供がそれでいいのなら、このタイミングで片付けてしまうのもありでしょう。
子供の気の済むまで
毎年短い期間だけ空を泳ぐ鯉のぼりに、心を奪われている少年もいるでしょう。
鯉のぼりは季節を感じられる大切な飾りでもあるので、子供が出してほしがっている間は出すという親もいますね。
ちなみに、鯉のぼりは子供の健やかな成長を願う縁起物なので、「何歳以上になったらあげてはいけない」などのルールはありません。
親の気の済むまで
子供の気が済んでも、親が出したければそうしても問題はないと思われます。
鯉のぼりがあがっているだけで季節感が出ますので、出ていて決して悪いものではないですよね。
やや過保護な気もしますが、子供が実家にいるうちは、結婚するまではなどという期限を設け、出し続けるのもいいかもしれません。
以上、鯉のぼりを何歳まで出すかについて、4つの説をご紹介しました。
「鯉のぼりは7歳までは出す」というのが本来の説ではありますが、家庭ごとの考え方を優先すればいいでしょう。
正しい期間は?鯉のぼりのあげる時期としまう時期をレクチャー


毎年のことだけど意外とよく分かってないのが、鯉のぼりをあげる期間ではないでしょうか。
こちらでは、鯉のぼりをいつからいつまであげればいいか、一般的に言われている期間について解説します!
あげる時期
鯉のぼりのあげ始めは、春のお彼岸が過ぎてからと言われています。
お彼岸の中日には「春分の日」があり、これを終えてから出すという意味合いがあります。



ちなみに、2025年の春のお彼岸期間は以下の通りです。
3/17(月)~3/23(日)
春分の日:3/20(木)
つまり、3月23日が過ぎれば、鯉のぼりをあげても支障はないと考えられそうですね。
とはいえ、そんなに早くあげるのもなあ…という気持ちがあるのも分かります。
このタイミングはあくまで目安と考え、4月中旬頃に出し始めるといいでしょう。
大型連休の始まる4月終わりなら、あげるタイミングも掴みやすそうですね。
しまう時期
あげる時期より、しまう時期の方がタイミングは掴みやすいです。
鯉のぼりのハイライトは、端午の節句である5月5日と言えるでしょう。
この日が過ぎたら、鯉のぼりをしまう家庭が多いです。
しまう時期にも特に決まりはないのですが、晴れた日にしまった方が、カビが生える心配も少なくなるでしょう。
梅雨の時季がやって来ることを考えても、遅くとも5月中にはしまいたいですね。
しまう時期が6月になる地域もある
一般的に端午の節句と言えば5月5日ですが、旧暦や月遅れといった形で、6月に行う地域もあります。
そういう地域にお住まいの方は、しまう時期がズレてしまいますね。
こういう場合、一般的なタイミングではなく、住んでいる地域の風習に合わせるのが一番だと思われます。
鯉のぼりの意味や由来って?今さら聞けないアレコレを紐解いてみた


鯉のぼりと言えば、男の子の飾り物!
恥ずかしながら、私自身もそのくらいの認識しかありませんでした。
実際、鯉のぼりにはどんな由来や意味があって、毎年あげられているのでしょう。
今さら人に聞くのはちょっと恥ずかしい意味や由来を、こちらで勉強して行ってくださいね。
鯉のぼりの意味
「鯉が滝を昇って竜になる」という、中国の故事をご存知の方は多いでしょう。
「登竜門」という言葉の由来にもなっていますね。
この故事にあやかり、男の子がたくましく成長し、出世するのを願う意味が鯉のぼりには込められています。
いわゆる、縁起物ですよね。
そもそも鯉は沼や池でも生きる生命力の強い魚なので、鯉のように力強く生きるようにという意味もあるとされています。
鯉のぼりの由来
鯉のぼりの由来は、家に男児が生まれたことを神様に報せ、守ってくれるようお願いするための目印だったと言われています。
そもそもは、武家の風習だったとも言われています。
家に男児が生まれた時、武家では馬印やのぼりを立ててお祝いをしました。
やがてその風習が庶民の間にも伝わり、鯉のぼりが考案されたとも考えられています。
鯉のぼりには、以上のような意味や由来があるとされています。
次の鯉のぼりは、そういった意味や由来をしっかり理解した上であげてみるといいですね。
まとめ
住環境の変化に伴い、大きな鯉のぼりを見る機会も減ってきたように思います。
しかし、形はどうあれ、子供の健やかな成長を願って鯉のぼりを飾るご家庭は多いですよね。
我が家もちゃんとした鯉のぼりは出せませんが、鯉のぼりの飾りを出して楽しんでいます。
鯉のぼりを何歳まで出すかについては、意外と知らなかった人が多いのではと感じています。
何となく出して、何となく出さなくなってしまったという事例も、よく聞きますよね。
さきほども触れたように、鯉のぼりは基本的には子供が7歳になるまで出すものとされています。
あとは家庭や地域の考え方を元に、個人個人で判断するといいでしょう。
鯉のぼりを何歳まで出すか分からなかった人は、今回の記事で謎が解けましたね。
お役に立てていたら、嬉しく思います。