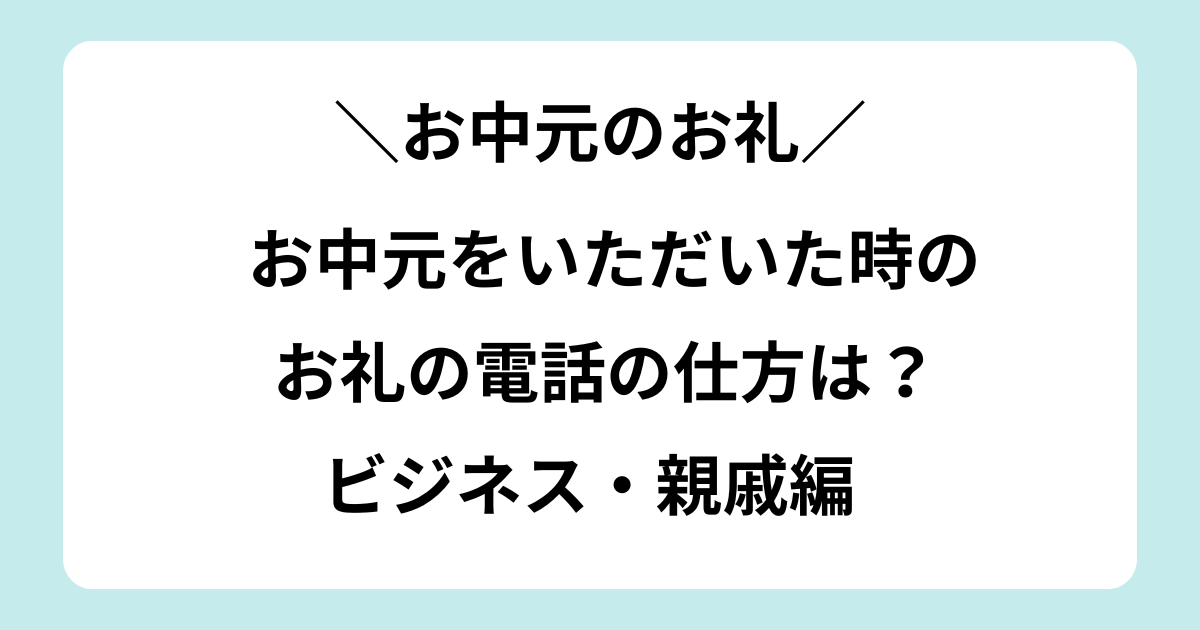お中元を頂いたお礼の電話の仕方をビジネス、親戚別にご紹介します。
また、お中元のお礼を手紙やはがきで送るときの例文、メールやlineで送るのは失礼にならないのかもお話ししますね!
会社や個人宛てに、ビジネス関連のお中元が届く人もいるでしょう。
まずはお礼の電話をかけるのがマナーですが、どうすればいいか迷いませんか。
そんなあなたのために今回は、「お中元のお礼の電話はビジネスの相手ならどんな風にするか」ということを解説していきますね。
お中元の季節を迎える前に、ぜひ予習してみてくださいね!
お中元のお礼電話はビジネスならどう言う?流れと注意点をチェック!

ビジネス関係でお中元をもらった時にはお礼状をだしますが、まずは電話にて感謝を伝えるのがいいでしょう。
会社宛ての場合、お礼の電話を社長の代わりにかける必要があるかもしれません。
いきなりお中元のお礼を電話でとなっても焦ってしまうので、電話でお礼をいう流れや注意点についてご紹介しますね。
お中元のお礼をいう電話の流れとは?
お中元をもらった相手の会社にお礼の電話をする場合の、具体的な流れをチェックしていきましょう。
①名乗る
何はともあれ、どこの誰が電話してきているのかを相手に知らせなくてはなりません。
会社名と、自分の名前を伝えましょう。
②担当者に取り次いでもらう
お中元を贈ってくれた相手、あるいはその手配を任されたと思われる担当者に電話を代わってもらいます。
③担当者に再び名乗る
担当者が電話口に出たら、再び会社名と自分の名前を伝えます。
④お中元へのお礼をいう
ビジネスの場に相応しい、丁寧な言葉遣いで感謝の気持ちを伝えます。
ただし、形式にとらわれ過ぎて、気持ちが入らないのはNGです。
あくまで、お中元を贈ってくれたことに対するありがとうの気持ちが伝わるようにしましょう。
⑤相手への気遣い
手紙でもよく見られる表現ですが、「ご自愛くださいませ」といった、相手を気遣う言葉を入れましょう。
⑥電話でのお礼になったことについて触れる
電話の最後には、取り急いで電話にてお中元のお礼をさせていただいたということにも触れておきましょう。
お中元のお礼を電話でする時の注意点とは?

流れを頭に入れたところで、お中元のお礼を電話でする時の注意点についても知っておくといいですよ!
電話する時間帯に注意!
お中元へのお礼の電話ですから、なるべく相手を煩わせたくはないですよね。
電話をする場合にはこちらの都合ではなく、相手の都合を優先して考えるようにします。
出社直後や退社直前といった時間は慌ただしいですし、お昼休みだと休憩の邪魔をすることにもなりかねません。
できればそれらの時間帯は避け、電話をしたいですね。
「すみません」はなるべく使わない!
お中元のお礼の電話に出た相手方からはおそらく、「大したものではございませんが」「お口に合いますかどうか」といった言葉が出てくるでしょう。
「いえいえこちらこそ、すみませんでした」などと返したいところですが、「すみません」はなるべく使わない方がスマートです。
代わりの言葉としては、「恐れ入ります」や「とんでもございません」が適しているでしょう。
というのも、「すみません」は本来謝る時に使う言葉であり、感謝の気持ちを伝えるものではないからです。
日常的には感謝する場合にも「すみません」を使いがちですが、お中元のお礼電話を取引先にする時には控えるようにしたいですね。
お中元のお礼電話を親戚にする場合は?2つのパターンを要チェック!

お中元のお礼の電話を親戚にかける場合、親しいかどうかでお礼の言い方も少し変わってくるはずです。
2つのパターンで解説していきます。
お中元をくれたのが親しい親戚の場合
お中元のお礼とはいえ、親しい間柄なら率直にお礼の気持ちを伝えればいいでしょう。
ビジネス関連のように、形式ばる必要はありません。
元気?
お中元を贈ってくれてありがとう!
体に気をつけてね!
ざっくりしていますが、こんな感じでも問題ないでしょう。
相手との親しさにもよりますが、電話後のお礼状も必要ない場合が多いです。
電話でお礼をいい、かつお礼状まで送ってしまうと、かえってよそよそしく感じる人もいる可能性があります。
お中元をくれたのがそこまで親しくない親戚の場合
ビジネス関係へのお礼ほど堅苦しくある必要はありませんが、それなりの形式でお礼をいうのが望ましいと思われます。
まず感謝の気持ちを伝え、近況報告なども入れるといいでしょう。
電話のために時間を取らせたことについて一言触れ、相手を気遣うメッセージを入れれば合格です。
お礼の電話を取引先にかける時には時間帯にも注意しますが、あまり親しくない親戚相手の場合にも、そうした方が無難でしょう。
相手の生活リズムを把握していないなら、早朝や深夜などを避けて電話するようにします。
相手が留守中の場合はどうする?
お中元のお礼電話をかけるも、相手が留守電の時もあるかもしれませんね。
お礼を留守番電話でしてしまうのは、問題ないのでしょうか?
留守番電話だった場合には、とりあえずメッセージを残しておきましょう。
お礼を一言述べ、改めて電話をかけることも伝えます。
タイミングが悪く何度かけても繋がらないという時は無理にかけ続けず、お礼状を送るならそちらでその旨に触れておくといいですよ。
お中元のお礼状の例文ビジネス編!役立つ書き方の形式を紹介!

先ほども触れた通り、ビジネス関連でお中元をいただいた際には、お礼状でも感謝の気持ちを伝えます。
こちらでは、書くにあたっての形式とお中元のお礼状の例文をご紹介します。
ビジネス関連で使えるお中元へのお礼状の形式
お礼状の形式を、書く順番でご説明します。
ビジネス関連のお礼状は、基本的に縦書きです。
お礼をいう相手が取引先でも親しい間柄の場合には、はがき(横書きも可)でのお礼状もよしとされています。
お礼状には、シンプルな便箋を使いましょう。

無地で白いもの、あるいは薄い罫線が引いてあるようなものが適しています!
①頭語
お礼状の書き始めを示す言葉です。
「拝啓」と書いておけばまず問題はないので覚えておくといいでしょう。
拝啓という頭後には決まった結びの言葉がありますので、そこにだけ注意します。
②時候の挨拶
季節によって、お礼状に添える文言です。
お中元へのお礼状ですから、7月か8月に使われる挨拶を選びます。
③近況を尋ねたり相手を気遣ったりする言葉
時候の挨拶には、「いかがお過ごしでしょうか」と近況を尋ねたり、「お変わりないでしょうか」と健康を気遣ったりする言葉が続きます。



詳しくは、後に続く例文を参考にしてくださいね。
④お中元への感謝の気持ち
お中元をいただいて嬉しかったという気持ちを記します。
少し堅苦しく感じるかもしれませんが、取引先には形式にのっとった書き方をするのがいいでしょう。
⑤相手を気遣う言葉
「ご自愛ください」などというように、相手を気遣う文言を入れます。
⑥結語
お礼状を締めくくるための言葉です。
頭語と対になった言葉を使う必要があり、「拝啓」に対する結語は「敬具」となります。
より改まった場合には、「謹啓」という頭語に「謹白」という結語で締めくくることもあります。
⑦日付と差出人氏名
日付と差出人の名前までしっかり書いて、ビジネス相手へのお中元のお礼状は完成します。
日付:お礼状を書いた日付→漢数字で書く
差出人:会社名・名前(役職があれば氏名の前に添える)



以上の①~⑦を踏まえて、お中元へお礼状の例文を見ていきましょう。
ビジネス相手に対するお中元のお礼状の例文
時候の挨拶や頭語・結語の組み合わせなどは、お礼状を書く時期や相手に合わせて変えてくださいね。
お中元のお礼に書く例文で親戚相手への書き方を伝授!


お中元をくれた相手が親戚であっても、お礼の電話→お礼状とするのが一般的なマナーではあります。
いざ書く時になって慌てないよう、親戚に対してお礼を述べる場合の言い方も押さえておくといいでしょう。
親戚相手のお礼状でも、ビジネスの取引先に出すお礼状とさほど違いはありません。
堅苦しさはいくらか控え、相手にお心遣いへの感謝の気持ちが伝わるようにしたいですね。
親戚に対するお礼状の例文
このような感じでお礼状を書けば、まず失礼にはあたらないでしょう。
親しい間柄の場合には、もっとくだけた表現を使っても問題ありません。
お中元のお礼はメールやlineでも大丈夫?伝える相手別に解説!


メールやlineは今や生活になくてはならないツールですが、それを使って、お中元のお礼をすることは可能なのでしょうか?
電話の仕方やお礼状の書き方が違ったように、ビジネス相手なのか親戚なのかによっても、答えは変わってきます!
こちらでは、ビジネスと親戚という2つの相手に対して、メールやlineでお礼を伝えてもいいのかについて解説していきますね。
ビジネス相手の場合
お中元を贈ってくれた相手がビジネス関連の人だった場合、メールやlineでのお礼は控えた方が無難です。
やはりここは形式にのっとって、電話でのお礼からお礼状という流れを取るのが妥当といえます。
受け取る相手次第ではあるのですが、まだまだメールやlineをお礼の手段として捉える人は多くないと考えられます。
相手によってはOKという場合もありますので、まったく不可というわけでもありません。
ただし、お中元のお礼をメールやlineで行う場合には、気をつけたいポイントもありますよ。
お中元に関するメールであることを分かるようにする
メールでお礼をいう場合には、お中元についての内容であることを分かるようにしておきます。
件名に「お中元をいただきました」などと添えると、相手も何のメールか分かりやすくて親切です。
メールの形式はお礼状と同じでOK
メールであっても、形式はお礼状と同じと考えましょう。
頭語・結語、時候の挨拶などを書きます。(頭語と結語については、メールでは省略される場合もあります)
また、メールでお礼をいう場合には、「取り急いで送った」というイメージが出るといいですね。
早くお礼をいいたかったのでメールしましたという気持ちが伝わると、なおよしです。
親戚の場合
メールやlineでやり取りする親戚は、そもそもがかなり親しい間柄といえますね。
あまり気負わず、普段通りの雰囲気でお礼をいうのがいいでしょう。
形式を重視した形にしたいなら、お礼状と同じように書けばいいですよ。
お中元を頂いたお礼の電話の仕方をビジネス,親戚別に紹介!手紙やはがきで送る場合の例文とメールやlineは失礼にならないのかも解説!まとめ
社会人になった、結婚した、ということでお中元の電話を初めてかけることになった人もいるでしょう。
そんなあなたにはぜひ、今回の記事を参考にしてほしいと思います。
特にビジネスの相手だと緊張してしまうものですが、お礼の言い方ばかりに気を配るのではなく、何よりありがとうの気持ちを伝えましょう。
お中元を贈る方も贈られる方も、気持ちよくありたいものですよね。