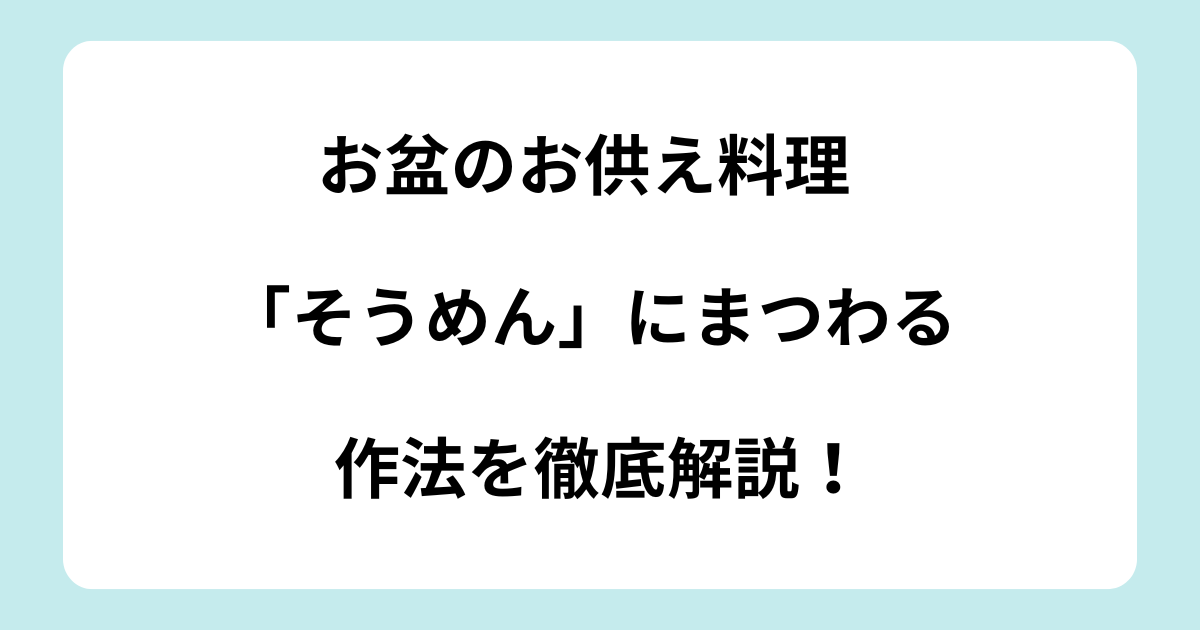お盆料理そうめんのお供えの仕方についてご紹介します!
お盆にはそうめん料理を仏壇にお供えするということを何となく知っていても、いざやるとなると、お供えの仕方に迷いますよね。
親がやっていて結婚後に自分が…という場合もありますね。
この記事では、
・お盆料理のそうめんのお供えの仕方
・そうめんはいつ飾るのか
・地域によっての違い
・お盆に食べたいそうめんレシピ
・お盆にそうめんを仏壇にお供えする意味や由来
について詳しくお話ししていきます。
今さら誰かに聞くのも億劫だという人はぜひ、今回の記事をお役立てください。

お盆にそうめんをお供えする方法やその意味、美味しいレシピまで一挙ご紹介します!
お盆のそうめんのお供えの仕方!やり方を2つの側面から解説!
まず、お盆のそうめんのお供えの仕方としては、次の2つのパターンがあるのを知っておきましょう。
- 行事食
- 盆棚飾り



それぞれの場合にどんなお供えの仕方をするのか、詳しくご説明しますね。
行事食としてのそうめんのお供えの仕方
「行事食」とは、仏様が召し上がるためのお供えです。
食べるということを前提としているので、茹でたそうめんにめんつゆもかけてお供えします。
お盆の時期になると、仏壇前に小さなお膳を用意することがありますよね。
これは「霊供膳(りょうぐぜん)」と呼ばれるものですが、地域や家庭によっては、こちらでそうめんをお供えする場合もありますよ。
盆棚飾りとしてのそうめんのお供えの仕方
ご先祖様の霊をお迎えするため、お盆には「盆棚/精霊棚」を飾ることもありますね。
お盆といえばお団子を供えるご家庭もあるかと思いますが、お団子と並んで、そうめんを飾る場合も多いです。
盆棚を飾る際には、真菰(まこも)というゴザを用います。
この真菰がある場合にはそうめんをじかにお供えし、真菰がない場合はお皿に載せます。
どちらの場合にも、そうめんの束を重ねるのがお供えの仕方です。
このように、そうめんのお供えの仕方としては2つのやり方があります。
それぞれの正しいやり方で、お盆のそうめんをお供えしてくださいね。
お盆お供え料理としてのそうめんはいつ飾る?


お盆にそうめんをお供えするのは何となく知っていても、いつ飾るのかについては知らなかった…ということはないでしょうか。
今さら誰かに聞くのも恥ずかしいというあなたのため、お盆お供え料理としてのそうめんをいつ飾るか、にスポットを当ててみていきましょう。
そうめんを飾るのはお盆3日目!
お盆お供え料理、つまり行事食としてそうめんを飾る場合、一般的にはお盆の3日目といわれています。
先ほど触れたようにそうめんは茹で、めんつゆと一緒にお供えしましょう。
ちなみに、飾りとしてお供えする乾麺のそうめんについては、お盆お期間中はずっと飾っておきます。
ただし、ここで注意したいのは、こういう風習には地域差や家庭でのやり方があるということです。
場所によっては、お盆にそうめんをお供えしない地域もあります。
そうめんのお供えの仕方や飾り方、そうめんを何日飾っておくのかなどについては、ご身内に相談するのもひとつでしょう。
お盆にそうめん料理をお供えするのは地域によって違いありって本当?


ここまで、お盆にはそうめんをお供えするという前提でお話をしてきたわけですが…。
確かに日本各地に残る風習ではあるのですが、地域によって違いがあるものだといわれています。
場所によってはそうめんでなく、別のものをお供えしたり食べたりという事があります。
そうめんではなくうどんという地域もある
地域によっては、お盆にそうめんではなく、うどんをお供えするという場所もあるのです。
これは行事食としても、盆棚飾りとしても同じです。
そうめんを、うどんに置き換えたと考えてください。
なぜお盆にそうめんをお供えするのかについては後で詳しく解説しますが、うどんにも同様の意味があるからと考えて差し支えないでしょう。
お盆に赤飯という地域も
お盆にそうめんではなくうどんをお供えするという風習も珍しいですが、他には、お盆に赤飯をお供えする地域もあります。
北海道や宮城、秋田などといった東北を中心とした地域では、お盆に赤飯をお供えします。
お盆といえばおはぎが一般的かと思われますが、赤飯にはおはぎと同様の意味があるとされているためです。
おはぎは小豆を使いますが、小豆の赤には魔よけの意味があります。
赤飯にも同じ意味を見出したため、これらの地域では赤飯をお供えするようになったのではと考えられています。
このように、お盆といえばそうめんという一般的だと思われていた風習にも、地域が変われば違いが生まれるということですね。
また、家庭のやり方によっても変わってきますので、一般的なお供えの仕方にとらわれず、柔軟に対応していきたいですね。
お盆に食べたいそうめんレシピ2選をご紹介!


お盆にそうめんをお供えするのに合わせて、家庭でもそうめんを食べることが多いですよね。



こちらではお盆の食事にもぴったりな、そうめん料理のレシピを2つご紹介しますね♪
へちまとそうめんの味噌汁
へちまとそうめんを使った味噌汁は鹿児島の郷土食であり、お盆に出すそうめんの精進料理としても重宝されています。
本州ではあまり食べる機会のないへちまですが、へちまには夏バテを防止してくれる嬉しい効果があるんですよ。
お盆の暑く、食欲のない時にもするすると食べられるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
=へちまとそうめんの味噌汁の作り方!=
- できれば煮干しから出汁を取り、先に味噌汁を作っておく。
- へちまは皮をむいて食べやすい大きさに切り、1の汁の中で柔らかくなるまで煮る。
- そうめんを茹でて器に盛り、へちま入りの味噌汁をかけてできあがり。



そうめんを味噌汁の中に入れて煮てもいいですし、仕上げにお好みでみょうがの千切りを添えるのもおすすめです!
わかめ入りそうめんチャンプルー
いつもの食べ方に飽きたら、そうめんチャンプルーを試してみてください。
そうめんとわかめ・豚肉の相性もよく、栄養もたっぷりの一品ですよ!
=わかめ入りそうめんチャンプルー 作り方!=
- そうめんは茹でて水洗いして冷やし、水気を切っておく。
- わかめは水で戻し、食べやすい大きさに切っておく。シイタケ・玉ねぎ・豚肉も、それぞれカットしておく。
- ごま油を熱したフライパンでまずは豚肉を炒め、シイタケ・玉ねぎ・わかめを加える。
- そうめんと加えて具材とざっと合わせたら、酒としょうゆ、塩コショウで味を調えてできあがり。



具材はお好みで揃えてもいいですし、そうめんに飽きたら豆腐を入れたチャンプルーにも変更できますよ。
以上、そうめんを使った2つのレシピをご紹介しました。
どちらも簡単で夏バテ予防にもなるレシピなので、お盆や子どもの夏休み中などに試してみてくださいね。
お盆にそうめんを仏壇にお供えする意味!知っておきたい4つの理由!


お盆にはお供え物として、そうめんを仏壇に飾ることも多いですよね。
しかし、そもそもどうして、お盆にはそうめんをお供えしたり食べたりという習慣が生まれたのか気になりますよね。
こちらでは、お盆にそうめんをお供えする意味を、その由来と共にご紹介していきます。
お供えする意味①幸せが続くことを願う意味
「○○の糸」という商品名のそうめんがあるように、そうめんは細く長い形状をしていますよね。
その見た目に、「幸せが細く長く続きますように」という思いが込められているという説があります。
つまり縁起を担ぐという意味で、お盆のお供え物になったとされています。
お供えする意味②お土産を持って帰る「紐」としての意味
お盆にはそもそも、ご先祖様があの世から里帰りする時期という意味がありますね。
久々に帰って来てくれるご先祖様を、お供えというおもてなしやお土産でもって出迎えます。
お盆が終わってご先祖様が帰って行く時に、お供え物を持って帰るわけですが、その時に荷物をまとめる紐として活躍するのがそうめんというわけです。
そうめんの一大産地である香川県小豆島のお盆では、ご先祖様のためにさらに工夫を凝らしていますよ。
小豆島のお盆ではそうめんを網のように編む、「負い縄そうめん」というものを飾ります。
こちらをお供えする意味もまた、ご先祖様がお土産を持ち帰るためなのですが、紐に比べて編んだものの方が丈夫そうですね。
どちらの場合も、山ほどもあるお土産をそうめんで縛って持ち帰る様子を想像すると、ちょっとほのぼのとした気分になりませんか。



お盆が、もっと身近に感じられそうですね。
お供えする意味③「手綱」としての意味
お盆にはきゅうりで作った馬、なすで作った牛をお供えするところもあるでしょう。
いわゆる精霊馬・精霊牛ですが、お盆にこれらの馬や牛とそうめんを供えることで、ご先祖様が牛に乗って帰る時の手綱になるといわれています。
お供えする意味④病気にならないように願う意味
お盆のそうめんには、疫病を予防する意味もあると考えられています。
そうめんがそのように考えられてきたのはいつからかというと、古くは平安時代からだったそうですよ。
その時代から既に、そうめんは熱病除けとしてお供え物にされていました。
食欲を失いがちな夏でも食べやすいそうめんは、現代でもまさに病気を防いでくれるありがたい食べ物といっても過言ではないかもしれませんね。
お盆にお供え料理としてそうめんを仏壇に飾る由来とは?


お盆にそうめんをお供えする意味について知ったのならば、その由来についても触れておきましょう。
お盆にそうめんを供える由来は、一体どこからきたのでしょうか。
七夕行事に由来
そうめんは平安時代より疫病の予防に重宝されてきましたが、これは、宮中の七夕行事においてでした。
この風習は今でもいくらか残っており、七夕にそうめんを食べる地域も珍しくありません。
最初は七夕にそうめんをお供えするという風習が、やがてお盆にも受け継がれるようになったと考えられています。
麦の収穫に由来
昔から、お盆の時期は麦の収穫にあたる時期でもありました。
そのため、お盆に麦(小麦)から作られたそうめんをお供えするのは、収穫祭としての意味もあるといわれています。
お盆にそうめんではなくうどんをお供えする地域があると触れましたが、うどんもまた、麦より作られている食べ物ですよね。
お盆にはなすやきゅうり、そうめんを供えますが、これはその時期に収穫できたものという意味があったのです。
旬のものをご先祖様にも分けたいという、昔の人なりの心遣いがあったのかもしれませんね。
お盆料理そうめんのお供えの仕方のまとめ
夏といえば飽きるほど食べることになるそうめんですが、お盆のお供え物としての、重要な役割もあったのですね。
そうめんをお供えする地域の人に、今回の記事を役立ててもらえたなら嬉しいです。
そうめんでなくうどんをお供えする地域もあるといいますし、同じ日本でも様々な風習があり面白さも感じられると思います。
お盆とそうめんにまつわる様々な意味や理由を知った今、次にやって来るお盆をまた違った感覚で迎えられるのではないでしょうか。
そしてこれからも、こういう風習を大切にしていきたいですね。