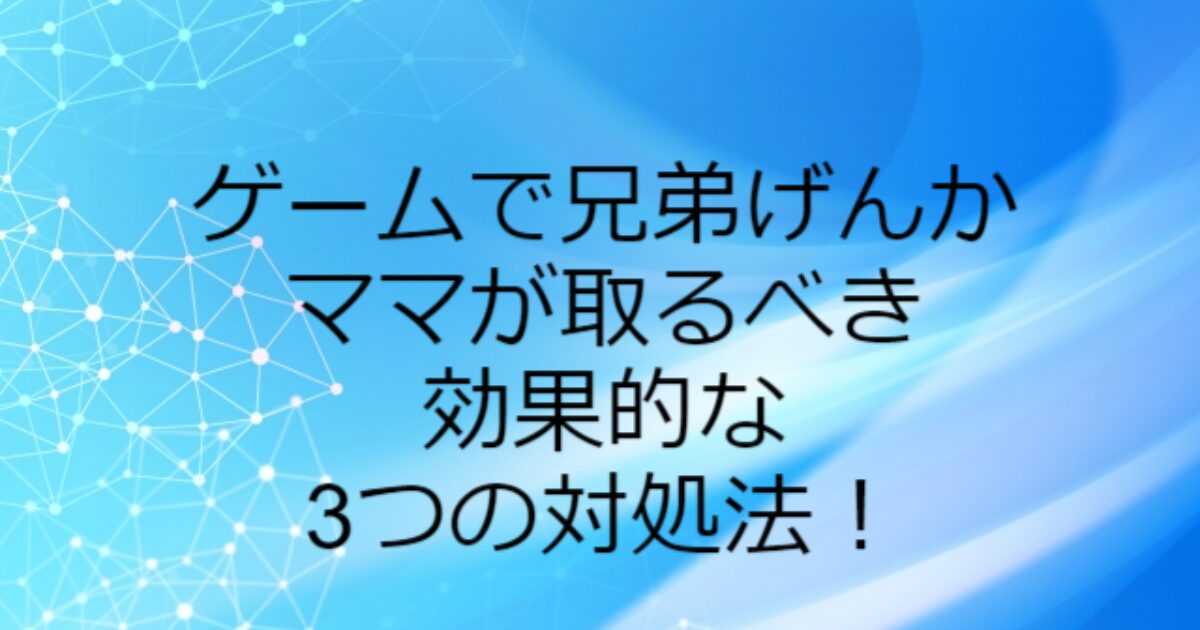子どもの大半がゲーム機を持つという時代で、兄弟でそれぞれゲーム機を持つということもあるでしょう。
そんな時に起こりがちなのが、兄弟喧嘩です。
ゲームから始まる兄弟喧嘩は、意外と多いものなのです。
ゲームで兄弟喧嘩が始まったら、ママはどうすればいいのでしょうか。
お困りママに、おすすめの対処方法をご紹介します!
ゲームを巡る兄弟喧嘩が起こったら?ママが取るべき3つの対策をご紹介
兄弟というものは、あらゆることが原因で兄弟喧嘩をします。
ゲームなんかはいい着火剤で、あっという間に兄弟喧嘩に火を点けてくれます。
ゲームが原因で兄弟喧嘩が勃発した時、一体どう対処すればいいのでしょう?

こちらでは、ゲームを巡る兄弟喧嘩の、効果的な対処法をご紹介しましょう。
ゲームを取り上げる
ゲームが原因で兄弟喧嘩をするなら、その原因であるゲームを取り上げてしまいましょう。
「お前のせいだ!」と兄弟喧嘩がヒートアップする可能性もありますが、喧嘩したところでゲームができるわけではありませんね。
すると、子どもなりに交渉に出てくることも考えられます。
「ゲームしたいから喧嘩しないよ!」と、兄弟自らが申し出る可能性もあります。
親にガミガミ言われて仲良くしようとするのは、実際難しいことです。
そうすることが得(=ゲームができるようになる)なのだと子ども自身が分かる方が、ずっと効果的です。
兄弟喧嘩をしたらゲームを取られる!
その経験が、今後の兄弟喧嘩にストップをかけてくれるかもしれません。
親が仲裁に入る
兄弟喧嘩の中には、子どもたちだけでは収集の付かなくなってしまうパターンもあります。
やがてはどちらかが暴力を使うこともあり、それによって怪我をすることも考えられます。
そうなっては困るので、やはり親の仲裁も時には必要なのでしょう。
冷静さを失った状態での兄弟喧嘩は、もはや子どもだけでは解決できません。
仲裁に入るからには、兄弟それぞれの話をよく聞き、公平な判断を下しましょう。
兄弟間に歳の差がある場合、どうしても上の子を叱りがちになってしまいます。
いつもそうでは兄はむくれ、いっそう弟に対して喧嘩を吹っかけるようになってしまうかもしれません。
下の子はしたたかな一面もあり、自分の立場を上手く利用する術を心得ていたりします。
弟には弟の悪い部分もあるはずなので、下だからというだけで大目に見ることはなるべく控えましょう。
兄弟喧嘩の仲裁に入って判断を下すことは、実はとても難しいことです。
いつもどちらかの肩ばかり持ってしまって悩むという人は、次の方法も試してみてください。
好きなだけやらせておく
それはあまりに無責任なのでは…と思われそうですが、それが一番いい対処法だと考える人は多いです。
たとえばママが間に入ってしまうと、どうしても親目線や大人目線での仲裁をしてしまいがちです。
- お兄ちゃんなんだから弟に優しくしなさい!
- 弟なんだから、お兄ちゃんの言うことを聞きなさい!
親からすればどちらも正論ですが、兄弟それぞれにとっては不服でもあります。
兄可愛さ、弟可愛さで、ママでも公正な判断ができないこともあるでしょう。
そもそも兄弟喧嘩というものは、どちらが悪いか明確な判断が難しいパターンが多いです。
言うなれば、どちらも悪いのです。
そこに双方が納得する結果をもたらしてやるのは大変なことなので、やりたいようにやらせておくという選択肢が生まれます。
兄弟間に年齢差があって、そこから来る体格差を武器に上が暴力を振るうなら、それは見過ごせません。
怪我をしそうな気配がある場合には、親が割って入る必要はあります。
我が家の息子たちも些細なことで衝突して兄弟喧嘩をしていますが、いつの間にか元のように、楽しそうに遊んでいます。
そういうのを見ていると、仲裁に入る意味はないのかも…と思う次第です。
ゲームを兄弟でやる時のルール!あると便利な4つの掟


ゲームを巡って兄弟喧嘩することが多いのなら、何らかのルールを作ることが必要になります。
兄弟喧嘩することなく子どもたちがゲームを楽しめるようにするには、どんなルールを作ればいいのでしょうか。
ゲーム<宿題とする
兄弟でゲームをする上のルールと言うより、ゲームをするにあたってのルールと言えるでしょう。
ゲームはあくまで、空いた時間でやることをルールとします。
まずは学校の宿題や準備を最優先として、それらができた場合のみ、ゲームをしていいことにします。
我が家もそうなのですが、上は小学生、下は保育園児(幼稚園児)といったパターンもありますね。
保育園児には宿題もなければ、自分で支度することもありません。
その場合には、兄に合わさせるのをルールにしておきます。
弟は何もやらなくていいからすぐにゲームできるとなってしまうと、兄に不満が生まれるのは間違いありません。
お兄ちゃんの準備が整ってから、一緒にゲームするというルールにしておくといいでしょう。
ゲームで遊ぶ時間を決める
ゲームには強い依存性があり、あと少しあと少しの積み重ねで、結局何時間もプレイしてしまうこともよくあります。
そういうことにならないよう、1日どれくらいゲームしていいのかということは、しっかりルールに組み込んでおきましょう。
たとえば、ゲームは1日1時間までと決めたら、子どもにはそのルールを絶対に守らせます。
ゲームに夢中になっていると、ここまではやりたいという欲求が子どもにも生まれます。
それを許してしまうと、ルールを決めた意味がなくなります。
どんなにいい所までやって来ていても、プレイ時間は厳守させます。
子どもには、それを分かった上でゲームをさせるようにしましょう。
ゲームのプレイを巡って喧嘩しない
ゲーム中に相手をバカにしたりして、それが元で兄弟喧嘩に発展することもよくあります。
余計な喧嘩が起こらないよう、ゲームのプレイを巡ってバカにしたり文句を言ったりしないようにルールを決めましょう。
「へたくそ」「お前のせいで負けた」など、ゲーム中に言ってはいけない禁止ワードを設けてもいいですね。
ペナルティの設定
ルールを作る以上、それを破った場合のペナルティも重要になります。
宿題より先にゲームをしてしまった、決めた時間以上にやってしまったなどという時には、ペナルティを課しましょう。
ゲームを巡ったルールを守れなかった場合、ゲーム機を取り上げるというペナルティが多く採用されています。
〇日間ゲーム禁止!といったペナルティを設ける人もいます。
軽過ぎるペナルティは、あまり効果がありません。
かといって、無期限禁止や重過ぎるペナルティにも反発が出る恐れもあります。
子どもにしてみたら1日ゲームができないだけでもソワソワしてしまうでしょうし、禁止期間は、ほどほどにしておきましょう。
それでもルールが守れないようなら、時には重過ぎる罰も必要にはなってくるでしょう。
一例ではありますが、子どもがゲームをする上でのルールをご紹介しました。
こちらの例を参考に、ご家庭ごとでゲームのルールを決められるといいですね。
親子で取り組む!ゲームとうまく付き合う方法を5つ考えてみた!


ゲームは子どもに悪影響を与えるとして、どこかいつも悪者のようになっています。
しかしひょっとすると、それは付き合い方が悪いだけなのかもしれません。
ゲームとうまく付き合う方法を知っていれば、子どもがゲームをやるのはマイナスなことばかりではありません。
とはいえ、子どもがゲームとうまく付き合うには、どうすればいいのでしょう。
やらせないのではなく、やるならルールを設けて!
子どもが自分もゲームをやりたいと言ってきたなら、まったくやらせないのではなく、ルールを決めた上でやらせることも考えます。
小学生くらいになると、友達からゲームの話を聞いてやりたがる子も増えてきます。
実際に一緒にやらせてもらって、自分もやりたいという欲求を高めることもあるでしょう。
子どもにゲームをやりたいという波がやって来た時、あなたならどうしますか?
ゲームはいろいろ悪い影響があるからやらせない!
そういう方針のご家庭もあるでしょう。
家庭にゲーム機1台ではなく、1人1台の時代である現在に、それはちょっと酷だったりもします。
いいか悪いかはさておき、ゲームが流行っているのは事実なのです。
友達の多くがゲームを持っているのに、自分は持ってない。
そういう状況を、子どもはとてつもなく歯痒く思うでしょう。
その不満が、日常生活に影響を及ぼさないとも限りません。
だったら、ルールを決めた上でゲームをさせることを許してあげましょう。
手に入れられない物に対しては興味が強くなったり、欲しくてたまらなくなってしまうものです。
ルールを守ることは絶対とし、子どもの欲求を満たしてあげることも大切です。
子どもに希望通りにゲームをやらせたことで、むしろ様々なことに意欲的に取り組むようになったという声も聞かれますよ。
ルール作りは親子で行う
ゲームをやらせるうえで、ルールは必須と考えましょう。
ゲームをすることはデメリットばかりではないとはいえ、手放しで与えるのはよくありません。
ルールを決める時には、親子で話し合うことをおすすめします。
親が勝手にプレイ時間やその他の約束事を決めたとしても、子どもが素直に従うかは怪しいところです。
毎日どれくらいゲームをやりたいのか。
そうするためにはどうしたらいいのか。
ルールを破った時はどうする?
こういったことを親と子で話し合い、親の目の前でルールを守ることを約束させます。
人は、誰かの前で守ると宣言した約束やルールは、心理学的な反応で守る傾向にあると言われているからです。
子どもも一方的に与えられたルールでない方が、自分に対する責任を感じやすくなるでしょう。
こういった理由で、ゲームに関するルール作りは親子でやるのが望ましいのです。
ゲームをやるのは親の前で!
ルールを決めてゲームをできるようになったら、ゲームは親の目の届く場所でやらせるようにしましょう。
子どもはどうしても楽な方向に流れてしまうので、親子で作ったルールも、安易に破ってしまうこともあります。
自分の部屋では好き放題にやってしまうことも考えられるので、やるのはパパやママの前でと、ルールに組み込んでおきましょう。
これと関連して、ゲームを始めた頃は、ゲーム機はなるべく親が預かっておくのがいいと思われます。
子どもを信用するかどうかの問題でもありますが、悪気がなくても、目に付けばやりたくなってしまうものです。
自分自身をしっかり管理できるようになるまで、ゲーム機は親の管理で使わせるのがいいでしょう。
親子でゲームをプレイしてみる
ゲームに悪い印象しか持っていないパパやママは、一度子どもと一緒に遊んでみることもおすすめです。
子どもが夢中になっているものに参加するのは、決して悪いことではありません。
最近のゲームはかなり工夫が凝らされているので、大人がやっても十分に楽しめます。
子どもと同じ時間を共有することで、子どもがなぜゲームをやりたがるのか、理解を深められる可能性もあります。
親が悪い見本になってはいけない!
子どもだけでなく、親もゲームに夢中になっている場合は要注意です。
当然ながら、親がゲームやり放題なのに、子どもに時間を決めてやりなさいというのは理不尽な話ですね。
スマホやパソコンなどで、ゲームにどっぷりはまってしまう大人もたくさんいます。
子どもにルールを決めてゲームをやらせる以上は、大人がその見本にならなければなりません。
子ども同様に大人もゲームのルールを設け、それを守る姿を子どもに見せましょう。
まとめ
我が家の息子たちも、ゲームが原因での兄弟喧嘩をよくします。
今はまだ、ゲーム機を持っていないお子さんも、TVのCMで見たり友達から話を聞いたりして、ゲームに興味を持っていることでしょう。
買ってくれとせがまれる日も近いだろうと、親として覚悟はしておいた方がいいですね。
そういう状況にあるパパやママは、たくさんいると思います。
そんなゲームは、兄弟喧嘩の引き金になりやすいアイテムとも言えます。
ゲームに熱中して興奮し、いつも以上に兄弟喧嘩しやすい状況になるとも言えます。
そういった兄弟喧嘩をまだ経験したことのない親も、心構えはしておきたいですね。
今回の記事が、その予習になってくれたら嬉しく思います。