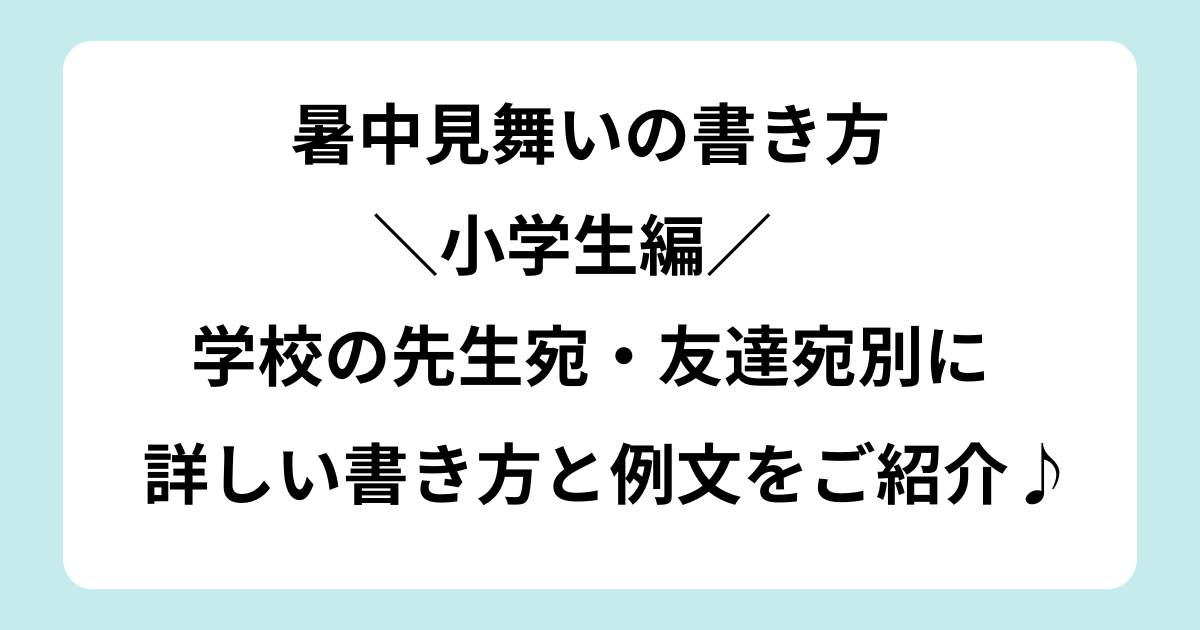暑中見舞いの書き方を小学生向けに解説していきます!
小学生にもなると、学校の先生に暑中見舞いを送る機会もありますよね。
親や学校からの働きかけで、暑中見舞いを書く子供も多いですね。
暑中見舞いの書き方を小学生の子供に教えたいけど、どうやればいいか分からないという方もいるでしょう。

今回はそんなお悩みにお答えして、暑中見舞いの書き方や小学校の先生宛、友達宛別に参考例文などもご紹介しますね!
暑中見舞いの書き方を小学生向けに伝授!書くのにおすすめな6つの話題!
暑中見舞いの書き方を、難しく考える必要はありません。
相手のことを思って、自分なりの言葉を綴ればいいのです。
大人ならそれなりにできることも、小学生には難しいこともありますよね。
そんな悩める小学生さんたちのため、こちらでは、暑中見舞いの書き方をご紹介しましょう。
書き方を参考に、自分なりの暑中見舞いを書き上げてみてくださいね。
① 暑中見舞いの挨拶
暑中見舞いの文面の冒頭には、「暑中お見舞い申し上げます」という挨拶を載せておきます。
まずはこの挨拶から始め、徐々に相手のことや自分のことについて書いていくといいでしょう。
② 相手が元気にしているか
暑中見舞いは、相手がどうしているのか気遣うための手段でもあります。
暑い夏は体調も崩しやすいので、元気にしているのか尋ねるのです。
そういうわけで、暑中見舞いの挨拶の次には、相手が元気にしているかどうかを尋ねる書き方がいいでしょう。
先生相手なら「お元気ですか?」や、友達に宛てて書くなら「元気?」と簡単に聞けばいいでしょう。
③ 自分はどうなのか
相手の健康についてこちらが聞くだけだと、相手もこちらが元気でいるのか気になるはずです。
相手のことを尋ねたら、自分のことも知らせておきましょう。
元気でいたなら、自分もそうであることを伝えます。
「この前まで風邪を引いていました」などと、どういう状況だったかを伝えてもいいでしょう。
④ どんなことをして過ごしているか/過ごす予定か
小学生だと、夏休みに入って会わない時間が増えると、お互いに相手が何をしているのか気になるものですね。
暑中見舞いを出す相手も、きっとあなたがどう過ごしているのか気になっているはずです。
夏休みは、話題になりそうなイベントが数多くあります。
海水浴、お祭、旅行など、自分が何をしていたか(これから何をするか)を、相手に教えてあげるといいでしょう。
⑤ これからの目標
・夏休み中には、25m泳げるようになりたい!
・自転車に乗れるようになりたい!
・宿題を早めにやり終える!
などなど、自分が目標にしていることを挙げてみましょう。
この話題も、決して難しく考える必要はありません。
仲のいい友達相手なら、「アイスの当たり棒を10本ためる!」なんていうのも、面白くていいのではないでしょうか。
⑥ 相手への気遣い
相手が元気でいるか尋ねて、自分の近況についても書きました。
いよいよ、暑中見舞いの文面も終わりに近付いてきています。
自分のことを書いて「ではさようなら」などと終わってしまうのではなく、最後にもう一度、相手のことを気遣います。
「先生も、元気で過ごしてください」や「風邪引かないようにね」といったことを書くといいでしょう。
暑中見舞いをもらった相手は、あなたの気持ちを嬉しく感じるはずです。
以上、暑中見舞いの書き方として、6つの話題を挙げました。
書き方としてはこのような流れになりますが、絶対守って書かなければいけないということではありません。
頭の挨拶、相手が元気か尋ねるといったことは、書き方として守った方がいいです。
自分が元気かどうかにも触れ、最後にまた相手のことに触れ、その間は自由に書きたいことを書けばいいでしょう。
このように、暑中見舞いは、何も難しいものではないのです。



上記の書き方を参考にして、あなたも小学校の友達や先生に暑中見舞いを書いてみてくださいね!
暑中見舞いを小学生が書くのに役立つ5つの例文を先生宛・友達宛て別に大公開!
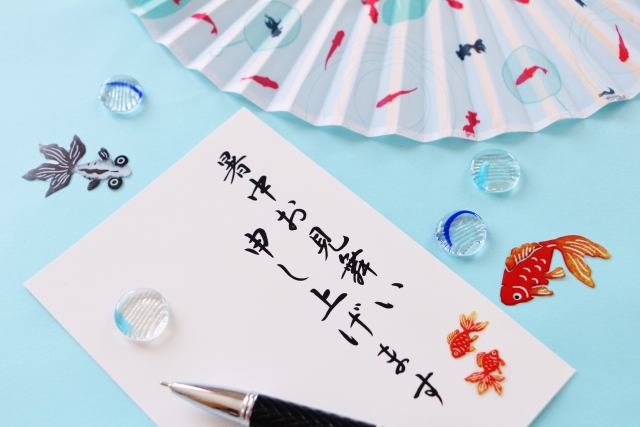
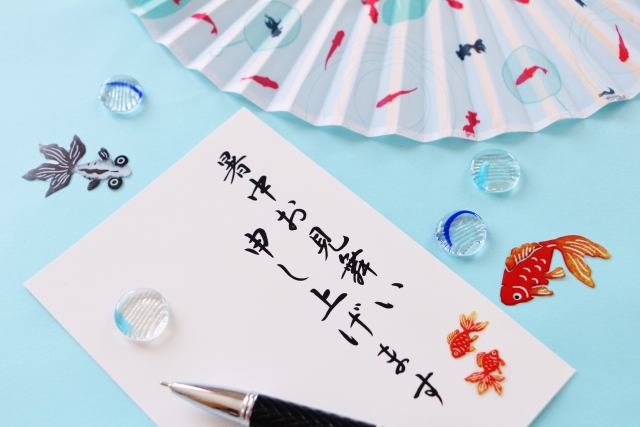
暑中見舞いを書くのに、お手本の例文があると嬉しいですね。
ここからは、さらに役立つように、小学校の先生と友達にパターンを分け、暑中見舞いにおすすめの話題を使った例文をご紹介しますね!
暑中見舞いの書き方①ラジオ体操
先生宛て編
小学生の女の子から、先生に宛てた暑中見舞いを想定しての例文です。
暑中見舞いの書き方に従って、先生の様子を尋ね、自分の近況を書いていますね。
ラジオ体操に休まず通いたいという、目標も添えてあります。
最後に先生の体調を気遣い、暑中見舞いを締めくくっています。
低学年の小学生の場合、もっと簡単な言葉を使って書くといいでしょう。
まだ文章が上手く書けない場合には、お手本で書き方を教えるなど、大人がサポートしてあげましょう。
同じような内容で、友達に暑中見舞いを宛てるとどうなるでしょう。
以下の例文を、参考にしてみてください。
友達宛て編
暑中見舞いの書き方②海
先生宛て編
友達宛て編
暑中見舞いの書き方③おじいちゃん/おばあちゃんちへ行った
先生宛て編
友達宛て編
暑中見舞いの書き方④夏祭り
先生宛て編
友達宛て編
暑中見舞いの書き方⑤夏定番の食べ物
先生宛て編
友達宛て編
以上、暑中見舞いにおすすめのテーマを挙げ、小学校の先生宛、小学生のお友達宛別に分けていくつか例文をご紹介しました。
例文でご紹介したテーマを、自分自身の話題に置き換えて書いてみると簡単にできますよ!
暑中見舞いを出す時期はいつ?知ってたつもりだけど、本当は?


これまで、暑中見舞いの書き方や例文について見てきました。
ところで、そんな暑中見舞いを出す時期はいつなのでしょう。
「夏休み中ならOKなのでは?」と、漠然と感じている人もいるかもしれませんね。
書き方を学んで書いた暑中見舞いですから、適した時期に出したいものです。
暑中見舞いを出す時期は、7月7日~立秋前日(8月初旬)までです。
それ以降は残暑見舞いとなり、残暑見舞いも、出せるのは8月23日までなのです。
どうしてこの時期に出すことになっているのでしょう。



詳しく見ていきましょう。
始まりは7月上旬より
暑中見舞いを送り始めることのできる時期は意外にも早く、7月7日ごろとされています。
小学生はまだ学校に通っているので、イメージとは少し違いますね。
7月7日は二十四節気のひとつである、小暑にあたります。
二十四節気とは、簡単に言えば、季節を表現するための言葉です。
春分や夏至、秋分、冬至といった言葉も、この仲間です。
さて、そんな小暑には、「だんだんと暑くなってくる時期」という意味が込められています。
暑さが増してくる頃だからこそ、暑中見舞いを出して、相手のことを気遣うのだと考えるといいでしょう。
終わりは立秋前日まで
立秋は、暦の上で秋の始まりを意味します。
そのため、暑中見舞いはその前日までに出すようにします。
2024年の立秋は、8月7日です。
8月上旬なんて、季節的にはまだまだ夏という感じですが、暑中見舞いはこの前日、6日までに出しましょう。
立秋以降は「残暑見舞い」になる
立秋までに暑中見舞いを出せなくても、残念に思う必要はありません。
立秋以降になると、暑中見舞いは「残暑見舞い」に変わり、最初の挨拶も「残暑お見舞い申しあげます」となります。
残暑見舞いにも、実は期限があります。
残暑見舞いの挨拶は、8月23日の「処暑」までに済ませます。
処暑は夏が過ぎる頃を意味していますので、残暑見舞いにしても、この時期までとなるのです。
このようなことで、暑中見舞いを出す時期が決まっています。
まだ学校に通っている小学生なら、学校が終わって夏休みに入ってから、立秋前日までに出すのがベストでしょう。



小学生向けの残暑見舞いの書き方はこちらの記事でご紹介しています!
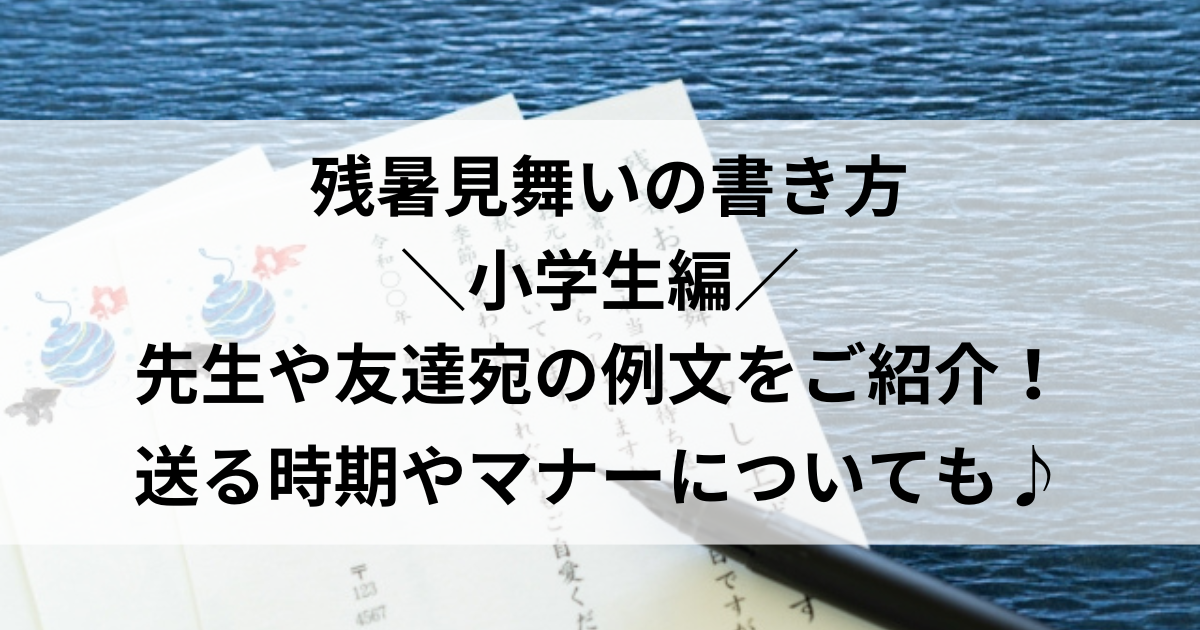
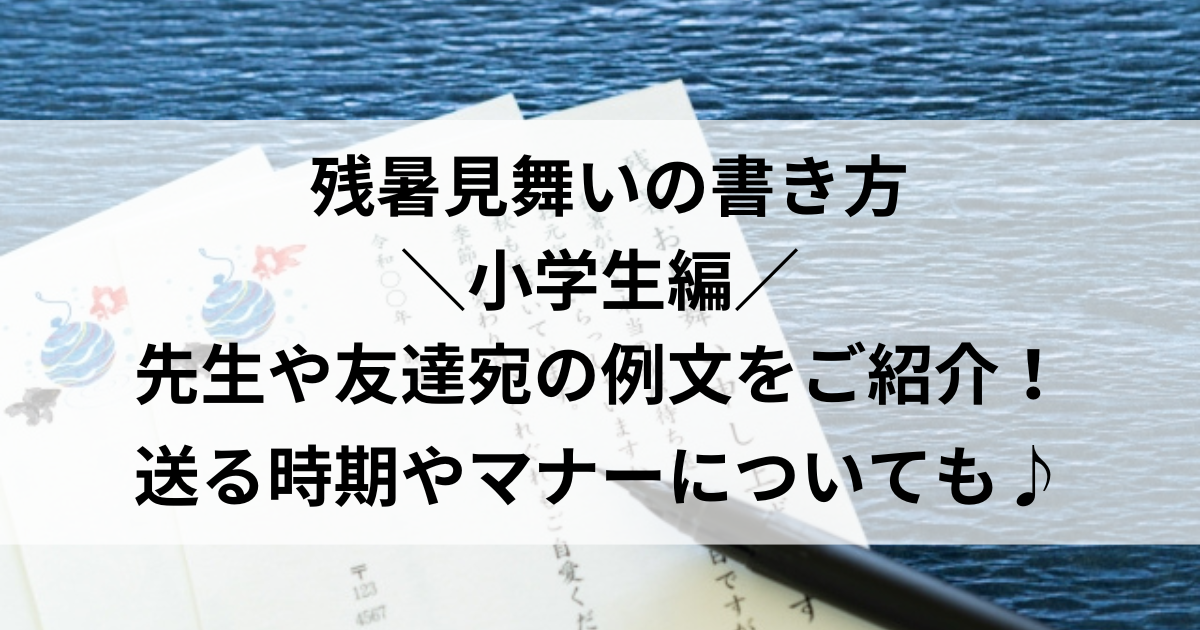
暑中見舞いの書き方を小学生向けに解説!まとめ
私は小学生の頃、夏休みに暑中見舞いを書くのが好きでした。
友達はもちろんのこと、先生にも必ず出していました。
インターネットや携帯電話、スマホの普及で、世の中の動きとして、ハガキで暑中見舞いを書くことはずいぶん減ったように思います。
それでというわけでもありませんが、私もいつ頃からか、暑中見舞いを書かなくなりました。
うちには小学生の息子がいるのですが、彼にはぜひ、暑中見舞いを書かせたいと思っています。
字を書く練習にもなりますし、相手のことを思って手紙を書くという習慣も身に着けさせたいです。
そういう考えを持つ親御さんは、きっと多いでしょう。
今回の記事を参考にして、小学生のお子さんに暑中見舞いの書き方を教えてあげてもらえればと思います。